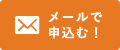- 西淀川区の個別指導塾なら【T's Lab】トップ
- ブログ
- 迷ったときに正解に近づく方法。
迷ったときに正解に近づく方法。
先日、社会の授業で日本の地形についての問題がありました。
川の名前を答える問題で、生徒は「木曽川」と「長良川」のどちらにするか迷ってました。
そのとき私は、「問題のレベルや問題を作った人の気持ちを考えるとどっちだと思う?」と聞いてみました。
すると、生徒は「木曽川だ!」と答え、正解することができました。
なぜ木曽川が答えになったかというと、
問題のレベルが基礎的なものが多い傾向だったこと、
木曽川の方が有名で覚えやすい、という点を考えたからです。
(ちがう子は長良川を知らずに木曽川と書いて正解していました)
つまり、単に知識を思い出すだけではなく、
「そのテストや入試レベルではどちらが問題に出されやすいか」を考える視点を持つことも大切なのです。
(レベルが高くなるとだと長良川や揖斐川が問われることもあるでしょう)
こうした考え方は、特に迷ったときに役立ちます。
覚えていることが両方あるとき、どちらを選べば正解に近いかを判断するには、
「出題者の意図」や「問題のレベル感」を意識することもポイントの一つになります。
これは地理だけでなく、歴史や公民、理科や国語問題でも同じです。
学校のワークの中でも、定期テストのレベルより明らかに高い問題が含まれてたりします。
もちろん、解けることにこしたことはないですが、解けなくても学校のテストでは高得点が取れたりもします。
勉強をしていると、すべてを完ぺきに覚えるのは難しいと感じることもあります。
そんなとき、単純に知識の量に頼るのではなく、
「出題されやすいものはどっちか」と考える癖をつけておくと、正答率を上げることができます。
過去問って同じのは出ないから何回もやっても意味ないんじゃないかと考える子もいますがそうじゃないんですね。
問題のレベルや傾向をしっかり理解することで迷ったときに正解に近づくことができるのです。
今回の木曽川と長良川の例は、その考え方がうまくはまったケースでした。
迷ったときに一歩立ち止まって「どちらが問われやすいか?」と考える習慣を持つことが、
テストでの得点アップにつながります。
そんなことを考えているT’sLabに興味のある方はお気軽にお問い合わせくださいね。
個別指導塾
T’sLab
つかもと研究所・おおわだ研究所