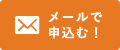- 西淀川区の個別指導塾なら【T's Lab】トップ
- ブログ
- 「○○」と言う子が増えている気がするシリーズ part2
「○○」と言う子が増えている気がするシリーズ part2
最近、テストの手ごたえを聞くと生徒からよく言われることがあります。
「できた!…あ、でもできたって言って点数悪かったら悲しいから、あんまりできなかったことにしとく」
ど、どういうこと!
できたけどできてないことにしておく!?
甘いものを食べたけど食べてないことにしとくみたいなこと!?
というのはさておき、ここ近年増えてきている気がします。
いわゆる「自分の評価を低めに言っておく子」ですよね。
今、SNSが生活の中で当り前にあり、目立ってしまうといろいろややこしい(だいぶ端折ってます)ので、
あまり大きく目立たないようにしようみたいな風潮になっているとのことです。
(誰かが言ってました)
でも、気持ちはわかります。
期待して、裏切られると傷つきますよね。
だから、先に自分でハードルを下げておく。
ある意味自分を守るための「安全策」なんです。
ただ、前回も書きましたが、思考のクセは厄介です。
この考え方がクセになってしまうと、本当の自信が育ちにくくなってしまいます。
よく考えてください。
本当に「できた」と思えてるのに、「できてない」ことにしてしまう。
がんばって解いた問題も、テストを受けながら感じた手ごたえも、全部「なかったこと」にしてしまう。
これはめちゃくちゃもったいないですよね。
どの問題がうまくいって、どこに不安が残ったのかなど、正直に言葉にできると学力は伸びやすいと言われています。
それが、「自信を持たないことで傷つくのも避けるクセ」がつくと、
よかったポイントも悪かったポイントも全部ぼんやりしてしまい、改善がしにくくなります。
ただ、子どもが素直に「できた!」言えるためには、聞き手が非常に重要になります。
子「今回できた!」でも、テストの点数はよくない。
大人「できたって言ってたやん!なんでこんな悪いの!」
先日、電車の中である親子がいて、子ども(小学校低学年ぐらい)が泣いてたんです。
親が「なんで泣いてるの?理由を言わないとわからないじゃない」みたいなことを言ってたのですが、子どもはなかなか言わなかったんです。
何回もしつこく親が理由を聞いて、やっと子どもは泣いてる理由を言ったんです。
そしたら、親が「そんな理由で泣くんじゃない!」と。
私は心の中で「え~~~っ!」と叫んでしまいました。
子どもが勇気を振り絞って言ったのにめっちゃ怒るんか~い!と。
(理由はよくわかりませんでしたが、とりあえず言ったことを認めてほしかった…)
これは言いたくなくなるだろうなと思っちゃいました。
子どもにとって、「できた」と言うのは勇気のいることかもしれません。
でも、その勇気が第一歩です。
そして、聞き手も言ったことをまずは全力で受け止めることが大事です。
たとえ、点数が思ったより良くなくても、それは自信を持った自分の否定にはなりません。
むしろ、「次どこを伸ばすか」が見える大事な経験です。
私たちは子どもたちが素直に「できた!」と言える環境を作っていきます。
そんな教室はとても雰囲気の良い空間に包まれていると思っています。
そんな個別指導塾T’sLabに興味のある方はお気軽にお問い合わせくださいね。
個別指導塾
T’sLab
つかもと研究所・おおわだ研究所