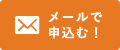- 西淀川区の個別指導塾なら【T's Lab】トップ
- ブログ
- 途中式を軽く考えていると危険です。
途中式を軽く考えていると危険です。
最近、生徒のノートを見ていて感じるのが、途中式の「我流化」です。
特に数学が苦手な子や伸び悩んでいる子に多く感じます。
例えば、
x+5-3x+8
=x-3x=ー2x +5+8=13
=ー2x+13
答えは合っているけど、式の書き方としては危ういです。
そもそも=は「同じ」という意味です。
「x+5-3x+8」と「x-3x」は同じではありません。
正しくは、
x+5-3x+8
=x-3x+5+8
=ー2x+13
3つの式は同じという意味です。
実は途中式というのは、「自分の考えを整理するための道筋」です。
正しく書ける子ほど、自分の頭の中で何をやっているかをはっきりわかっています。
「こうだからこう」と根拠をもってゴールまで進むことができます。
逆に、途中式がごちゃごちゃしている子は、
式の意味を理解しないまま数字を動かしがちです。
つまり、「式がきれいに書ける=考え方が整理されている」ということなんですね。
また、途中式の乱れは学年が上がることに大きな差になってきます。
方程式、関数、図形の証明などどれも「道筋を立てて考える」ことが求められるからです。
途中式を整える習慣がないと、文章題や応用問題で急に手が止まる子が多いのもこのためです。
「答えが合ってればいいじゃなか」と思うかもしれません。
でも、途中式は「思考の跡」です。
だからこそ、T’sLabでは「途中式の書き方」まで丁寧に見ていくことを大切にしています。
そんな個別指導塾T’sLabに興味のある方はお気軽にお問い合わせくださいね。
個別指導塾
T’sLab
つかもと研究所・おおわだ研究所