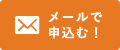- 西淀川区の個別指導塾なら【T's Lab】トップ
- ブログ
- 生徒から教わることもある。
生徒から教わることもある。
先日中3生の数学を指導していました。
√の計算で、乗法公式を使って解く問題がありました。
(2√5-√2)2
この問題を指導するときに、
(x-a)2=x2ー2ax+a2
という乗法公式を使います。
なので、
(2√5-√2)2
=(2√5)2-2×2√5×√2+√22
=20-4√10+2
=22-4√10
になるのですが、途中式の -2×4√5×√2 の部分が結構混乱する生徒がいます。
√の中も2倍して 4√20 にしたり、そもそも2倍をし忘れて 2√10 にしたり…
公式自体覚えにくいようで、では公式を覚えず(2√5-√2)(2√5-√2)=
で考えてみて分配法則でやるか!と伝えようとしますが、
めちゃくちゃ効率悪いのでお勧めはしていません。
どう指導したらわかりやすだろうかと悩んでいた時、
先日指導した生徒は、
(2√5-√2)2
=(2√5)2-2√10-2√10+√22
=22-4√10
としたんですね。
-2×2√5×√2 を -2√10-2√10 と書いていました。
これをみて、「なるほど!その手があったか!」と思いましたね。
確かにこれでも解くことができますし、
考え方は合っています。
(2倍すると同じ数を足すという表現の違いです)
( 13×2 と 13+13 の違いです)
しかも、苦手な子はこれの方が間違えにくいとも思います。
「2√5と-√2をかけ算して、それを2回書いたらいいで」と指導することができます。
これを実際に別の生徒に指導すると、「公式よりかはやりやすい」と言ってました。
生徒たちを見ていると、解き方や考え方も人それぞれです。
もちろん、間違えて考えている子には修正していきますが、
「その考え方めっちゃいいやん!」という場合は、その考え方を違う生徒にも伝えることもあります。
いいものはどんどん取り入れて、アップデートしていきたいと思っています。
個別指導塾
T’sLab
つかもと研究所・おおわだ研究所