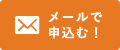- 西淀川区の個別指導塾なら【T's Lab】トップ
- ブログ
- 辞書を引くのもいいかもしれないという話をカーナビと本の地図から考えてみた。
辞書を引くのもいいかもしれないという話をカーナビと本の地図から考えてみた。
今回は「ネット検索と辞書の違いをカーナビと本の地図で考えてみた」という話をします。
最近、自分の住んでいる地域の紙の地図を見ました。
地図を眺めていると、「この道はここにつながっているんだ」とか「ここにこんなお店があるんだ」とか、
今までは気にしていなかったことが見えてきたりします。
ここで、ふと思ったことが。
車でどこか行くとき、私はカーナビを使います。
いろんなルートを探してくれるし、上手に案内してくれます。
とても便利です。
でも、よくよく考えると、目的地までの道以外はほとんど目に入りません。
で、本や紙の地図の話です。
本や紙の地図を広げると、「この近くにこんな大きな公園があるんだ」とか、
先ほども言ったように「その先にはこんな道につながってるんだ」という発見があります。
カーナビでは見えてない世界が、紙の地図では見えるんです。
これって、勉強の調べ物でも同じことが言えるのではないかと思ったんですね。
わからない言葉や単語などを今は簡単にネットで調べられます。
これはどちらかというとカーナビみたいなやり方。
確かに早いし、欲しい答えにすぐたどり着けます。
辞書を使うと、その言葉の前後にある他の言葉も自然に目に入ってきます。
「こんな言葉もあるのか」とか、「似た意味だけどちょっと違う単語もあるんだ」とか、
カーナビ的には見つけられない気づきがあります。
辞書の方が時間はかかるかもしれません。
でも、この「寄り道の中で生まれる発見」があるかどうかが、2つの大きな違いではないでしょうか。
確かに効率だけを求めたらカーナビやネット検索の方が便利かもしれません。
でも、「気づく力」や「視野の広さ」みたいなものを育てるには、あえて地図や辞書を開けてみるのもいいかもしれません。
勉強って、答えではなくて、その過程で何かに気づけることが大事だったりします。
こんなことを思った今日この頃でした。
個別指導塾
T’sLab
つかもと研究所・おおわだ研究所