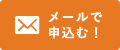- 西淀川区の個別指導塾なら【T's Lab】トップ
- ブログ
- この出来事を私はこう解釈しました。
この出来事を私はこう解釈しました。
本日は「授業をしていて私はこう解釈した」という話をしていきます。
先日、生徒に漢字の書き問題をさせていたときのことです。
全40問のうち、初めはなんと20問も空白のままでした。
半分わかっていない状態。
本人も「わからへん」と少しお手上げ状態でした。
でも、私は《直感でわからないと思ったらすぐ空白にする癖のある》この生徒に
「わからなかった漢字は、全部10回ずつ書いて覚えてもらうで」と伝えました。
生徒は「え~~~~っ!それはやだ!」と。
そして、生徒は空白になっている問題を再びにらみ始めました。
すると、そこから書ける漢字が10問ほど増えたんです。
あれだけ「わからへん」と言っていたのに。
この不思議な現状どう思いますか。
私は次のように解釈しました。
生徒は漢字を「思い出した」可能性が高い。
自分から頭を動かした。
てことで、「やらされている勉強」が「自分の頭を使う勉強」に切り替わったのではないかと。
ただやり方や答えを教えてもらう勉強ではなく、「自分の力でなんとかしよう」とすることで、脳がフル回転した。
その結果、『思い出す努力』をすることでやっと出てくる知識や考え方が、ピョコっと出てきたんでしょうね。
勉強はもちろん、わからないところを教えてもらうことも大事です。
でも、それ以上に「思い出そうとする時間」が大切です。
それが、記憶として定着し、この記憶たちがたくさんあることで思考力が身についてきます。
私たち講師側は、わからないときにすぐに答えを与えるのではなく、
「考えさせる時間」を作っていくこともとても大事だと感じています。
今回の出来事で生徒も「ずっと問題見てたら思い出してきたわ」と言って手ごたえを感じていました。
以前のブログにも書きましたが、テストは習ったことしか出ません。
その記憶を脳のどこかの引き出しから取り出すための『思い出す努力』をする癖をつけていきたいですね。
そんなことを考えている個別指導塾T’sLabに興味のある方はお気軽にお問い合わせくださいね。
個別指導塾
T’sLab
つかもと研究所・おおわだ研究所